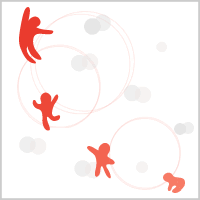「中等教育とJHL:アカデミック・ランゲージとアイデンティティ」
津田和男(国連国際学校、 New York)
Ⓒ2003 TSUDA
母語・継承語・バイリンガル教育研究会
「もう一つの年少者日本語教育−継承語教育の課題 」
パネル2「中等教育とJHL:アカデミック・ランゲージとアイデンティティ」
津田和男(国連国際学校、 New York)
キーワード:内発的、自省的、自助的考察、アカデミック・ランゲージ、アイデンティティ、教育のパラドックス、ナショナル・スタンダード、継承語教育、インターナショナル・バカロレア、教育としての日本語
序
この論考は、2003年5月25日に日本語教育学会が一橋大学で開催した春季大会にて日本で「継承語教育」にかかわる初めてのパネルを組んだことを記念して発表したものを、今後の継承語教育に対する発展を期待して再考を重ね、新たに書き直したものである。当日の発表は予定稿とパワーポイントを使用したこと、パワーポイントで使用した図は、予定稿執筆時点とは2か月以上の時間差を経て、より発展した意識を盛り込んでいること、予定稿を越える課題や事項が含まれていたことから、この論考では両者の意識を整理してまとめておきたいと考えた。さらに、学会発表時に、聴衆からの興味関心があるという声や、私の発表時における用語は学際的バラエティーが多く、日本の聴衆にとって不慣れな用語であったりするという声があったのと、この発表自体が、2003年の継承語・バイリンガル研究会の予定稿的要素を含んでいたとの理由で、再度書き改めようと思いついた次第である。
それ故、基本構成としては2003年春季の日本語教育学会の予定稿に従うが、その都度パワーポイントでの発表にも言及しておくことにする。また、学会大会での発表以後考えた問題などにも触れて提示したいと思う。特に、日本語教育学会発表以後、日本でもREX-NETのNPO立ち上げ、国際理解教育学会での自己の発言、全海研(全国海外研究)でのパネル、アメリカでの『銀河』製作(季節シリーズ第2巻の発行)、ノースカロライナでの発表、ヨーロッパでのパネルの思考の過程などがこの執筆時と重なるので、そこでの問題意識が絡んで提出されていることも理解していただきたい。
1. 実践者としての私の立場:内発的、自省的、自助的考察
青少年の学習者を対象とする継承語教育の研究は、単にいわゆる「研究」という立場で推し進めるだけでは不十分である。「教育としての日本語教育」(津田, 1994)は、次のような姿勢から出発している。第一に実践者と学習者の相互の内発的、自省的、自助的な展開による。いわゆるアカデミックな研究で行われる数量的な処理やエスノグラフィーの観察という方法は取らずに、内発的、自省的、自助的に実践の面から継承語教育に取り組む。継承語研究がまだ始まったばかりであることと研究者自身が広い層をなしていず、また、フィールドでの実践が研究にも大きな影響を与えることが明白であるからだ。
この継承語のフィールドでは実践者自身の内発的な忍耐を伴う創造力や、常に現実課題に対する内省的な評価力が、また、他者とともに経済的にも政治的にも心理的にも、自助的集団による問題解決能力が必要である。そのためには、一般の教育現場と継承語教育の現場とを比較する必要がある。継承語学習者にとっては、社会化のプロセスとアイデンティティの確立が複雑に絡み合っているのである。したがって、単純な類型論で語るわけにはいかず、内発的、自省的モデルを、個人にも地域社会にも役に立つという自助的な観点から、構築しなければならないのである。
まずは、私の立場を鮮明にしたいと思う。実践者としてのそれを私の立場とした。これは当研究会の基本的な規定が研究者の立場となっていることに対して自己背反している。なぜなら、私は実践者の立場を崩していないだけでなく、実践者が持つ研究者に対する優位性も表明しているからである。日本の伝統的態度からいえば、生意気な不謹慎な態度である。しかし、21世紀に入った今日、実践者であり、研究者であるといったような改めてルネッサンス的状況が生まれているのである。一見、私の立場はその意味では自己背反を犯しているように見えるが、むしろ、自己はこの自己背反律の中に大きな意義を見出している。内発的であれ、自省的であれ、自助的であれ、かなり自己背反的な要素を持っていると思われる。
「内発的」は夏目漱石が外国から日本に帰って気付いたことである。それは西洋に出かけ、彼の体験を通して日本の発展を考えた時、外発的な刺激によって発展するものではなく、内発的発展の必要性を訴えたのである。また、1997年にハマーショルド財団や鶴見らよって提唱されたものでもある。いままでの経済発展はヨーロッパをモデルにしてきた。自分たちによる発展の原理を西洋モデルではなく、自分たちが悪戦苦闘して築き上げた自分たちの文化から引き出そうというのである。ただし、そこには様々な混乱と葛藤を乗り越えるキーパーソンがいるといわれている。私たちが継承語を語るときこのキーパーソンは単に一人の孤高な存在ではなく、集団的で地域的な力の想定が必要になってくる。
次に、なぜ「自省的」なのかというとこれは「内省的」という言葉とも結びついているといえる。自省的とは柳田国男がかれの民俗学の中で民俗学は内省の学問だといったことに結びついている。また、内省論はヨーロッパ哲学の中でも古代から展開されている学問体系であるが、内省が実践活動に結びつくことはなく、宗教性や瞑想性に結びついている。われわれにとっては内面的な自省も実践的な内省も相互補完的だと考えている。
また、「自助的」とは生徒も教師も自助的にならざるを得ないし、自助性を意識化しなくてはならない。自助的であることにおいて、自助的アイデンティティの確立に大きな影響を与えることになる。精神障害者などの自助グループが話題になっている昨今であるが、社会の周辺にいるもの同志の自助努力がいかに大きな力を働かせるかなどが課題である。さらに、従来の教員中心主義の教授法に対するアンチテーゼでもある。生徒同士の自助努力によってより学びの可能性を切り開くものである。勿論、他者の立場を受け入れるという多様性の受容がそこに流れていることは確認しておきたい。その意味では多分に互助的なのであるが、敢えて自助的であるというのはその集団のもつ自立性も焦点としておかなければならないという理由である。
自助性・内発性・自省性の相互作用により、共同集団行為による学習の認知過程が明らかになると思われる。すなわち、共同集団学習がもつ積極的な価値を見つけ出せるのではないかということであり、少なくとも私にとっては過去の30年間において一定程度の成果が上がっていたと思われる。生徒の生活背景の多様さや学年の壁の乗り越えによる自助集団の形成が、共同性と多様性の合体の中でそれぞれの立場で行われてきたと思う。
第二に、私自身が教師であり、カリキュラムを作るという立場から、継承語教育が持つ教育上のパラドックスをまずしっかりと自覚する必要がある。教育というものがつねに社会のプラスの価値を志向するがゆえに、教育者はマイナスのものを切り捨てていく傾向をもつ。教育が評価を導入する限り、この問題を避けて通ることはできない。カリキュラムは常にその社会のある目標に向かっての到達点を基礎にしている。評価はそのカリキュラムにおける生徒の到達点と照らし合わせて評価されるため、到達点に達しないものはマイナスの評価が下されることになる。
継承語の場合、親社会(親が属していた継承語社会)の価値が評価基準になる。生徒たちが属している社会は親社会に対して言語的には上位社会になるので、継承語の親社会に対してはマイナスイメージがある。従って、生徒たちが属している子社会は、親社会に対して下位社会となるが、価値基準はまず、マイナスの価値をもつ親社会に対して価値を見出さなければならない。そのうえ、子供たちは自分の言語環境にも、従わなければならない。それ故に、二重のパラドックスを生徒たちは抱え込むことになる。
どんなにがんばっても、親の持つ価値からは評価されない。継承語は常に本国のことばに比べられ、マイナスに設定される。また、頑張らなければ、通常における社会同様に、マイナスの評価をうける。その上、子社会の言語の習得と継承語言語習得の両方に時間を費やして、継承語言語習得が時にはプラスに見えたり、時にはマイナスに見えたりする。主要言語の場合は、一般社会からプラスの価値づけがされているのに対して、継承語はマイナスの価値づけがされているという事実がまず存在する。それゆえに、マイナスを単にプラスにするというだけではうまくいかない。継承語学習者がこのパラドックスにみごとに立脚しているという構造自体を明らかにしなければならない。それ以上に、現在ニューヨークなどでは、一般社会自身の多重言語化がより進み、英語がその社会の言語として君臨していない状況も表れてきている。また、移民地域の変容によって様々な継承語同士のぶつかり方が現れてきている。スペイン語や中国語や韓国語が平然と存在するニューコーク市の場合、公立高校では25か国語が学校内で自然に存在することがあたり前のこととなっている。私の学校ではそれ以上に125か国の生徒が存在し、70の母語の異なった生徒たちが存在する。その上、日本人とフランス人の親がアメリカで生活するという例のように親社会の言語環境も重層化し始めている。
2. インターナショナル・バカロレア(IB)における言語教育方針の歴史的背景とその内容
IBプログラムに継承語教育が認定されたのは1997年である。日本語に限らず、グローバリゼーションの中で、それまでの言語教育体制では世界的な言語環境の変化に対応できなくなったためと考えられる。このような変化が起こるに当たっては、言語習得の難易度(日本語や中国語などアジアの言語には時間がかかる)やアフリカなどの多言語社会の問題を指摘しておきたい。内発的な変動の兆しがそこに読み取れるからである。
IBの継承語教育では、言語面の教育だけでなく、新しいコンテンツを含んだ、いわゆる「教育」そのものが要請されている。様々なトピック、例えば「変化」、「グローバル」、「言語/文化」、「メディア」、「社会」、「文学」について、多様なコミュニケーション様式で、かつ 様々なオーディエンス (audience) を意識した表現行為が要請されている。母語では自然体で無意識に可能なことも、継承語の場合は、意識的かつ段階的に指導し、表現を捉える過程を意識化しなくてはならない。このプロセスそのものが、内発的、自省的、自助的な教育に寄与するのである。
ここでは、今年の3月に行ったATJニューヨーク大会のSIGの会で発表したものの一部を少し加える。(津田, 2003) IBの継承語教育は学習言語の課題となるテーマをトピック別に用意すると同時にコミュニケーションの様式とオーディエンスの多様な存在を意識している。すなわち、言語の国内の学習者ならば自然にこれらの言語の形態に対応するのに対してその様々な様式や存在の多様性を意識化した方法論が必要であると説いているのである。
コミュニケーションの様式の多様化とは文学形式だけでなく、ジャーナル形式、会議形式、新聞形式、歌謡形式、メディア形式、広告形式など様々なコミュニケーションの様式が考えられる。またオーディエンスの様々な形態、例えば、若者向け、大人向け、学識経験者向け、子供向けなどと、二人の会話と三人参加のインタビューなどをコミュニケーション様式と組み合わせ、トピックもそれに合わせるようにカリキュラムを作る。
評価の段階でも以上の多様性がはかれる形式を採用して、内容の比較やトピックの様式の比較だけでなくコミュニケーションの様式の比較にまで及んでいるし、オーディエンスへの意識も要請されている。
3. 最近の継承語教育の動向とその特徴
日本語教育全般の動きの中で、米国ニューヨーク州を中心とする新しい継承語教育の動きと特徴を捉え、「内発的な模式」(鶴見, 1997)のケースとして考察する。米国北東部での中等継承語教育は米国内での戦前のハワイ型や戦後のカリフォルニア型とも異なった最近の新しい継承語教育であり、その継承語教育運動が内発的にニューヨーク市やプリンストンで独自のものとして開発されてきたことによる。そこにはキーパーソンと思われる教育実践者の実験の成果があり、それが新しい世界の教育運動と呼応していることが特徴である。
まず今回のパネルでの問題提起(中島, 2003)では、継承語教育が外国語教育(JFL)、第2言語教育(JSL)とどう異なるかについて、教師、学習者、教育形態、教授法、評価の諸点から比較する。更に継承語教育の枠組みの特徴を5つ挙げる。少数言語であることから来る学習者自身の継承語に対するマイナスの価値付け、教育の場が家庭と課外の教育機関であるために認知面の言語能力が伸びにくいこと、学習者の知的発達、人間形成(アイデンティティを含む)、情緒安定に密接に関わる言語習得であること、周囲の少数言語集団との関わりの中での学習であること、教育介入の方法が世代によって異なること。学齢期の途中で移動した準一世の場合は母語の保持・伸長が中心課題になるが、現地生まれの二世児になると継承語をゼロからどう育てるかが問題になり、三世、四世児以降は、継承語が生活上の機能を失い、言語文化集団のシンボル化する(Isajiw,1987)。しかし、継承文化存続のためは、継承語の活性化や再獲得が不可欠であり、その方法として唯一有効だと考えられるのが、学校教育機関の中に組み込まれた継承語イマージョン教育である(Fase et al, 1992)。
4.ナショナル・スタンダードと継承語教育
米国のナショナル・スタンダード(1999)をJHLの観点から考えたい。ヨーロッパ諸言語の学習と比較して、日本語学習には膨大な時間がかかる。習得時間の膨大性を、内発的、自省的、自助的に超越するという視点から、ナショナル・スタンダードは、JFLと比べて、よりJHLに応用可能だと思われる。なぜなら、ナショナル・スタンダードに掲げられたK-16の継続的言語教育の方向やIBで取り上げられたA2 language programは継承語教育とも重なるからである。JSLやJFLの学校でK-12ましてやK-16の継続性を持っている学校は極めて少ない。ところが継承語教育なら親との協力をふくめて長い間サポートが可能である。これは、むろんJFLへの多大な努力を否定しているものではない。むしろ、JFLがよりK-16の一貫性を追及することを目標として、実現してもらいたいものである。ただし、JHLが現在K-16の継続性という問題を私的にも公的にも実現できる可能性を大いに孕んでいるという指摘はできるのではないかと思う。従って、簡単な計算で1年間に100時間が直接授業時間とすると、12年間でやっと中級に達することになる。いかに中級にJFLやJSLで到達するのが大変かが分かろう。継承語教育では家庭内での努力によって生活言語はほとんど問題のないケースが多いわけであるから、出発点がJFLやJSLと変わってくる。継承語教育では、生活言語の中でも待遇表現などいろいろ問題があるが、やはり、学習言語が問題となってくる。また、ナショナルスタンダードでもIBでも内容重視や他学科との連携がうたわれていることなどから、明らかに生活言語だけでなく学習言語の重視の方向が見えている。例えば、ナショナルスタンダードでは文化(Cultures)や他学科との連携(Connections)は明らかに標準課題であるし、IBでもトピックの課題も同様な問題を含んでいる。
ナショナル・スタンダードに掲げられたK-16の継続的言語教育の方向やIBで取り上げられたA2 language programは継承語教育とも重なる。先の中島の問題提起にふれて考えると、ナショナルスタンダードのような展開が可能になれば、継承語のマイナス面に対して学校のシステムの中で単位制として社会化され、プラス面が出る。教育の場が学校内へとヘゲモニーの関係がプラスになる。学習者の知的、情緒的アイデンティティの回復がスタンダードでは他学科、文化、社会、比較の中でおこなわれる。IBでのカテゴリーの選択が学習者に明白な意識化を喚起する。継承語集団の社会化と個人化となる。入り口の多様化と出口の多様化を2つのプログラムでは可能としている。そして、ライフロングの学習過程が提唱されるべきである。
5.アカデミック・ランゲージと中等教育のあり方
中等教育の継承語プログラムでは、アカデミック・ランゲージ習得のため、内容重視の言語教育アプローチをとっている。その習得プロセスは、認知科学的方法や内発的、自省的、自助的な方法を通して展開される。
もういちど教育の現場に立ち戻って考えたいと思う。すなわち、中等教育に興味を示している皆が必ず対面する問題である。近年日本でも学級崩壊や教育の荒廃が叫ばれている。それはグローバルな世界の近代化のなかで、より崩壊の速度を速めているように見える。アメリカにおける教育の危機は1980年代にその頂点に達したと思う。特に、中等教育におけるエンタープライズ型の誰のニーズにも合わせたスーパーマーケット型の中等教育は暴力とドラッグの巣となった。その反省から新たな小集団による様々な教育システムや指導法が開発されていった。
たとえば、チャータースクールの地域への導入、マグネットスクールやオルタ-ナティブスクールによる地域内における組替えで新たな可能性を引き出す試み、コーポレートプランニングによる小集団学習内の相互自助学習の効果、クリティカルシンキングによる問題発見の見直しから解決への新たな道筋、ポートフォリオによる学習過程での理解に関する学習者・教育者・親・学校組織からの透明性のある評価基準の設定などである。
日本では1980年代から、明治近代に作り上げてきた近代位階制から近代的な機能分化制へと変わった。そしてこの間の教育現場は位階制的な教師の権威を失う過程であった。それまでの日本の教師は、教育上の権威を提示することで、上意下達の位階的システムによって教育できた。しかし、80年代以降では近代的なシステム社会になり、あらゆるところで機能的なシステムが代替可能になって問題を解決し、その問題を平準化するために他者がいつでも入れ替わる個体として扱われる社会になった。しかも、そうなりつつも、旧来の教育指導方式で対応せざるをえなく、学校での暴力や学級崩壊現象がおきた。日本でも90年代の後半に入ってスクールカウンセラーの導入、エンカウンターやピアサポートプログラムの欧米からの導入によって新たな学校の復活が始まっている。
奇しくも、日本における総合教育の導入とアメリカにおけるナショナル・スタンダードの問題は二つの国の負の面を見せることになった。日本ではカリキュラム作りの主体である教師の問題解決能力のトレーニングがいままで放置されていたことに教師自身が気付き始めたことがあるが、旧来の位階制的な評価基準だけを取り上げる外部の圧力によって文部科学省内で学力低下が問題視され始め、本来のマルティインテリジェンスとしての多様な教育目標に対する総合教育の無視の路線が始まりだした。それに対して、アメリカではナショナルスタンダードの導入で教師のカリキュラム作りの積極面より、評価基準による地域の学力上昇のための標準テストの導入が地域内の学校への圧力となりはじめた。
日本では個人として学校社会で生きる目標の一つとして今までの相対評価から絶対評価へと移行している。これは位階制的な制度に対して、より近代的な個人主義の顔を伴うが、社会全体の個人性の移行にもかかわらず、社会は旧式の位階制としての受験方式を手放していない。これからはアメリカのように「学力」だけでなく「ボランティア」や「課外活動」までも評価基準に入ってくるであろう一方で、生徒たちは受験の波からは逃れられないであろう。それ故、新たな受験指定校の復活による位階制の復活が進行している。グローバルな教育の総合的な始動と国内的な位階制的な教育の動きの狭間に継承語教育は遠く位置しているが、影響を受けることは間違いもない事実である。
それ故に、現状の分析による影響以上に、教育の持っている原理的なパラドックスの上での影響が必然的なものとして現れてくる。教育のパラドックスは絶えない。教育は常にプラス価値を志向しているので、常にマイナスを作り出してきた。「良い子」を作り出すために、「問題児」をどうしても作り出してしまう可能性がある。特に相対評価はそのような基盤にたっているが、現在の教育は日本だけでなくアメリカでも、その根底に、評価に身を置く自分を「あざける」一方で「ガリ勉をする者に対して勉強なんてしていないかっこよさ」を自己主張するという矛盾をはらんでいる。
先にも述べたがこのような一般的な教育のパラドックスに対して教育というものがつねに社会のプラスの価値を志向するがゆえに、教育者はマイナスのものを切り捨てていく傾向をもつ。継承語教育も評価を導入する限り、この問題を避けて通れない。継承語の場合、カリキュラムは常にその社会のある目標に向かっての到達点を基礎にしているのとは別に、その社会の下位社会の目標に焦点があっている。一般には評価はそのカリキュラムにおける生徒の到達点と照らし合わせて評価されるため、到達点に達しないものはマイナスの評価が下されることになる。主要言語の場合は、一般社会からプラスの価値づけがされているのに対して、継承語はマイナスの価値づけがされているという事実がまず存在する。それ故に、継承語学習者がこのパラドックスにみごとに立脚しているという構造自体を明らかにしなければならない。一般の教育の社会では、「他者を蹴落とす」競争をさせながら、「みんなで高めあう共同体」を作り出そうとしていることを踏まえた上で、共同体の中に特殊自助集団を作り上げなくてはならない。継承語における継承語自助集団は、継承語学習者の個々人の多様性を認めた上で「みんなが高めあう集団」を形成していかなくてはならないという成立条件が必要である。
教師らもこの多様性を認めておかないと価値の固定化が始まり、自助集団そのものが簡単に崩壊する。一般的な教育では比較的一元的な原理によって設定されるが、ここではそのような原理の導入が集団の崩壊か集団の位階制的な変質を生むことになる。教師の側のグローバルな視点形成とカリキュラム作りの具体化の中に、つねに内発的で自省的なプログラム作りをしなければならない。これはある意味で、いままでの「教授学習法」による情報伝達過程の考え方、すなわち教師が知識の情報源であり、生徒はその情報を解読するという考え方を否定することである。今後は、生活の形式や言語ゲームになじむことから始めてその言語活動全体に参入する経験を通して、自己生成的理解をする方法がとられなくてはならない。特に学習言語では一方的な知識の情報伝達ではなく、生徒や学習参加による(あるいは大人の参加者を含めて)対話と復活を通して自己生成を行わなくてはならない。
一方、学習言語の現地社会と継承語社会の多様な解釈の容認をファシリテーターとしての教師は見定めておかなくてはならないし、最低限の言語や知識のコーチングやアカデミックな徒弟制度など様々な方式と多様な学習様式を取りいれなくてはならない。つまり、学習言語の獲得に対する概念のあり方とテキスト論的な多様性を常に考慮に入れなくてはならないし、具体的な指示を多様な視点と積極的な学習介在のあり方を踏まえた上で提示しなくてはならない。
学習言語の学習環境などを考察しつつ、中島の問題提起を考えてみると、継承語のマイナス面と学校のマイナス面の中で継承語教育の位置を見定めるところから始める、ヘゲモニーの関係を意識化して自助グループを作る、知的、情緒的アイデンティティの意識化をしてカリキュラムをつくる、継承語集団との社会化と個人化をはかり多様性に応える、出入口の多様化は必然的に形成しなくてはならない。
6. カルチュラル・スタディーズにおけるアイデンティティ研究
カルチュラル・スタディーズのアイデンティティ研究(吉見, 1999)を参考に、まず米国における言語と若者文化とアイデンティテイの関係を考える。つぎにマイノリティー言語の立場から、言語と他者のアイデンティティとを比べ、継承語学習者のアイデンティティを内発的、自省的、自助的に解明し、模式的なものとして理解する。
テクスト論として始まったカルチュラル・スタディーズは、意味とはつねに特定のコンテクストに縛られて、いつでも特殊な言説の編成や発話の戦略、言語ゲームのルールに依存するという事実に敏感だ。あるテクストがどのような場で生成されているのか?どのような条件の下で、そのテクストは流通しているのか?それを読むオーディエンスや消費者はどのような人々で、いかなる歴史の契機とかかわり、どんな組織や言説の構造がそこには働いているのか?そして以上のような要素を形作ってきた、より広い意味の伝統や歴史の力とはいかなるものか?(A Dialogue, Hall、16)
それゆえに、カルチュラル・スタディーズは存在よりも生成変化のプロセスを重視する。アイデンティティはそれが捜し求めてきた歴史的な過去の中にその起源を見出そうとするように見えるが、実際には存在よりも生成変化のプロセスのなかで、歴史、言語、文化の資源を使うことである。「われわれは誰なのか」「われわれはどこから来たのか」が問題ではない。重要なのはわれわれは何になることができるのか、われわれはどのように表象されたのか、他者による表象が自分たち自身をどのように表象できるかにどれほど左右されているのかということである。(Identity, Hall、12)
カルチュラル・スタディーズの他者性やカルチュラル・スタディーズのオーディエンス(吉見, 99)がもっている問題はサブ社会の考察を可能にし、その中での生成的なアイデンティティを形成している。この課題は継承語教育の中で実践可能な課題として問われるのではないかという予感のもとに本稿では考え出されたものである。
7.中等教育における継承語とアイデンティティの形成
ニューヨーク地区の中学生、高校生対象の継承語教育の新しい動きをモデルとして、継承語学習者のアイデンティテイの形成プロセスを内発的、自省的、自助的、模式的に提示する。
教育自体のグローバルで機能的な関係意識が崩壊する中で、教師主導型によって生徒を教育する上意下達方式での教育技術論から、生徒の理解生成を中心とする生徒-教師による共同組織型の教育論が本格的な議論の対象となってきている。継承語教育は継承語社会が少数言語であることから来る学習者自身の継承語に対するマイナスの価値付け、の中で学習者は自己のアイデンティティを機能的に価値付けする(即時的にプラス価値として継承語を位置付けることはできない)ことは、もはや出来ないし、特にグローバリゼーション以降の現代のアイデンティティは流動的で多様な要因があり、ある時は優位な要因があっても、永続的な束縛とはならない。現代の継承語教育はこのグローバリゼーションと関係している。ニューヨーク付近におけるこの30年間の日本語継承語教育の動きは、この100年の日本語継承語の大きな流れの中でも特に流動的で不確定かつ懐疑的な経験に満ちている。
この間、特に70年代から現在にかけて、日本のグローバル化の中で問われた新たな海外子女の集団とは別に継承語学習者の存在が浮かび上がっている。70年代から80年代では海外子女の影に隠れていた継承語学習者の第3の波が現在大きく現れている。たとえば、北東部における小都市の日本人補習校の危機は、あきらかに継承語学習者の学習の問題点を見事に浮き彫りにしている。日本国内の学習過程を規範とする海外子女教育ではなく、外国語教育としての日本語教育とも違う日本語継承語教育の充実の問題である。それは、学習者の知的発達、人間形成(アイデンティティを含む)、情緒安定に密接に関わる言語習得である。社会の機能分化の中で機能的理解から理解の生成変化のプロセスの中でアイデンティティが問題となる。(重要なのはわれわれは何になることができるのか、われわれはどのように表象されたのか、他者による表象が自分たち自身をどのように表象できるかにどれほど左右されているのかということである。)(Identity, Hall、12)
それ故に、現地の学校社会の学習社会と継承語教育における内容重視の教育をすり合わせていかなくてはならない。そこでは、内容把握の方法、テクストのクリティカルな読みやオーディエンスに対する読み、発表表現の内部構造学習に対する具体的なカリキュラムが組まれなければならない。そのためには幅広く文学テクストや一般社会のテクストに対する読みの強化、情報調査の方法の学習、作文や発表に対する自己評価や他者評価などが設定されなくてはならない。また、相互批判の場の形成をファシリテーターである教師は作り出さなくてはならない。
以下に続く課題は先の中島問題提起を受けているし、それ以上に、アメリカでの教育実験や教育運動は、日本で取り上げられた様々な試みとともにより検討されることになると言っておきたい。そして、中島の問題提起を再考してみると、教師、学習者、教育形態、教授法、評価の諸点を比較して気付いたことから継承語教育の枠組を考え直すと以下のことが考えられるのではないだろうか。
少数言語であることから来る学習者自身の継承語に対するマイナスの価値付けについては、継承語のマイナス面と学校のマイナス面の中で継承語教育の位置を見定めるところから始める。しかし、以下に示される様々なカリキュラムと学習課題に対して積極的で多様性のある態度が必要である。
特に日本から来る教師は、近代的でしかも前近代的な制度に支えられてきた問題をしっかりと自覚していないと、簡単に日本的権威主義や日本的利己主義から来る放棄の姿勢に陥りやすい。なぜなら、日本人がこの数十年の近代化から超近代化のプロセスで、二つの近代化を乗り越えた時に、前近代的と近代的な部分を残したからである。この近代的な制度に支えられてきた問題とは、教師は近代社会に特有な機能システムとしての教育システムにおける機能的役割をもっている同時に、その立場は位階的な前近代的秩序思想に裏打ちされたものである、という点である。
教育の場が家庭と課外の教育機関であるために認知面の言語能力が伸びにくいことについては、学習言語の強化を図り、自由でクリティカルな態度と創造的なアイデアの産出を目指し、ヘゲモニーの関係を意識化して自助グループを作る共同の場の自助的な構築が必要である。
学習者の知的発達、人間形成(アイデンティティを含む)、情緒安定に密接に関わる言語習得であることについては、知的、情緒的アイデンティティを意識化したカリキュラム作りが必要である。
周囲の少数言語集団との関わりの中での学習であることについては、継承語集団の社会化と個人化をはかり多様性に応えるようにしなければならない。
教育介入の方法が世代によって異なることについては、出入口の多様化は必然的に形成しなくてはならない。 以下、上記の課題達成には次のような具体的な課題が提出されるはずである。
グループ学習と学生徒弟制、コーチング
自己史と日本近代社会史とのかかわり
演劇的な読みの可能性と多角的な視点の確立
オーディエンスへの認識と実際
発表と相互批判
身体性を含めた読みの可能性
発表時における質疑応答の自律化とその許容性
地域や自助的なグループの自律性
地域支援と継承語社会と日本人及び日本社会のグローバルな多様なつながりの形成
などがある。
また、上記の課題を内発的に自省的に自助的に解決することで、新たな発展が期待できるし、これは継承語社会の集団の自助であり、教師自身の自助でもあることも記しておこう。
<参考文献>
Chamot, A.U. and J.M. O’Mally (1994) The CALLA Handbook:Implementing the Cognitive Academic Language LearningApproach. Reading, MA:Addison-Wesley.
Shrum.J.L and Glisan. E. W (2000) Teacher’s Handbook. Heinle and Heinle.
National Standards, ACTFL Series. (1999) National Textbook Company.
Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century (1999) National Standards in Foreign Language Education Project.
International; Baccalaureate (1996) Language B
International; Baccalaureate (1996) Language AB Initio
International; Baccalaureate (1997) Language A 2
International; Baccalaureate (1998) Language A 1
吉見俊哉 (1999)『カルチュラル・スタディーズ』岩波書店
鶴見和子 (1996)『内発的発展論の展開』筑摩書房
石戸芳嗣(2000)『ルーマンの教育システム論』